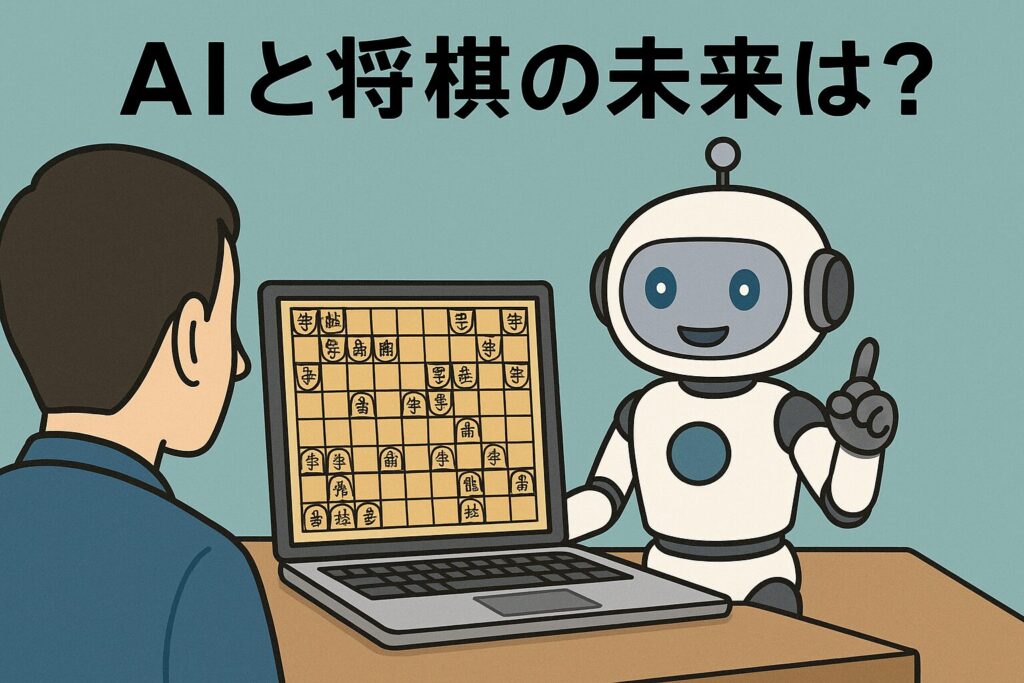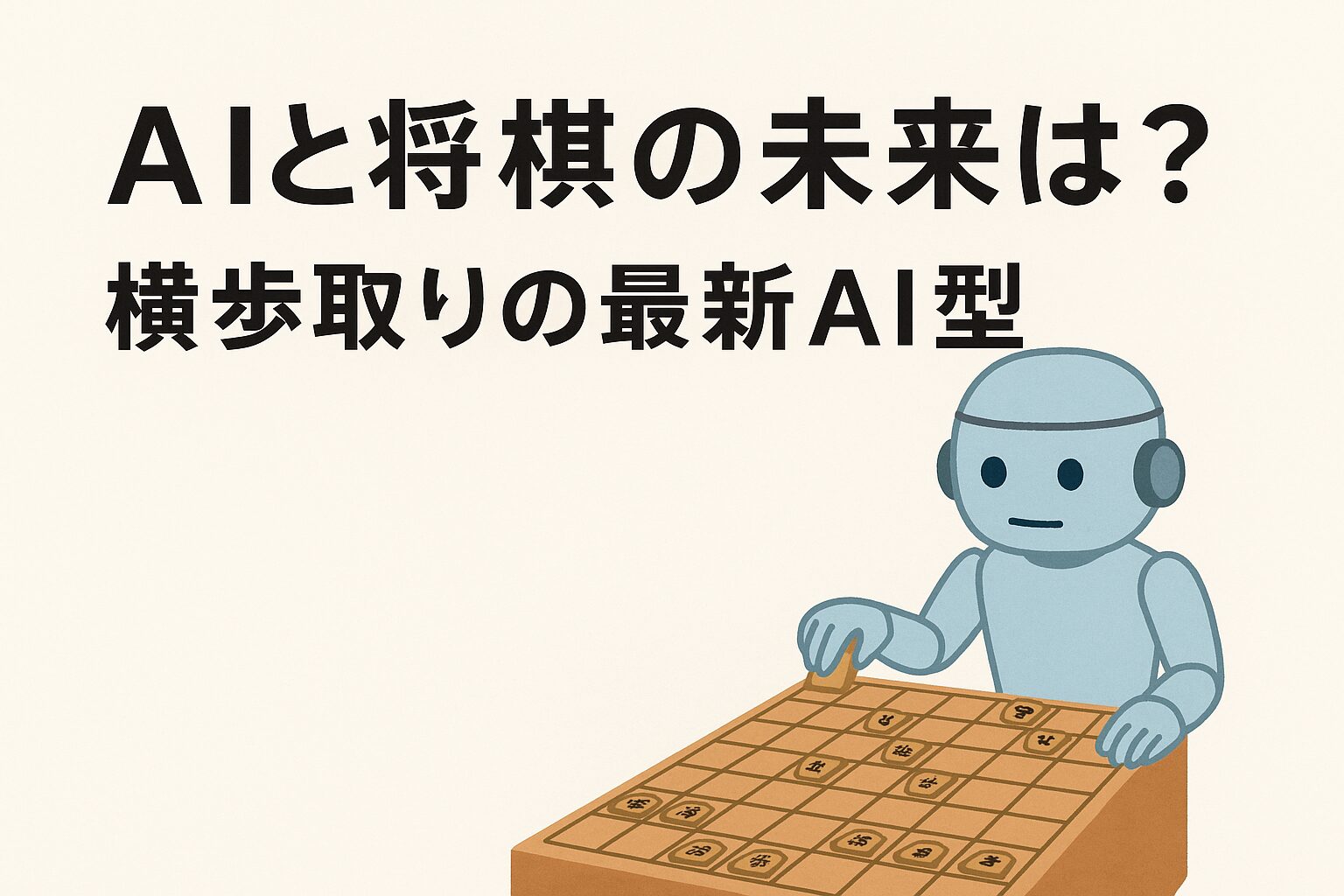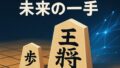近代将棋に疎い私にAIが教えてくれたこと
昨日のブログで、すでにAIソフトが「定跡なるもの」を考え、作り出す時代に入っていると述べましたが、近代将棋に疎い私にとっては、そのあたりの情報はまるで霧の中です。将棋ソフトの進化について、書籍や専門誌にあたってみても理解が追いつかず、まさに“苦しい時のAI頼み”という諺が欲しくなるほどです(勝手に作りました)。
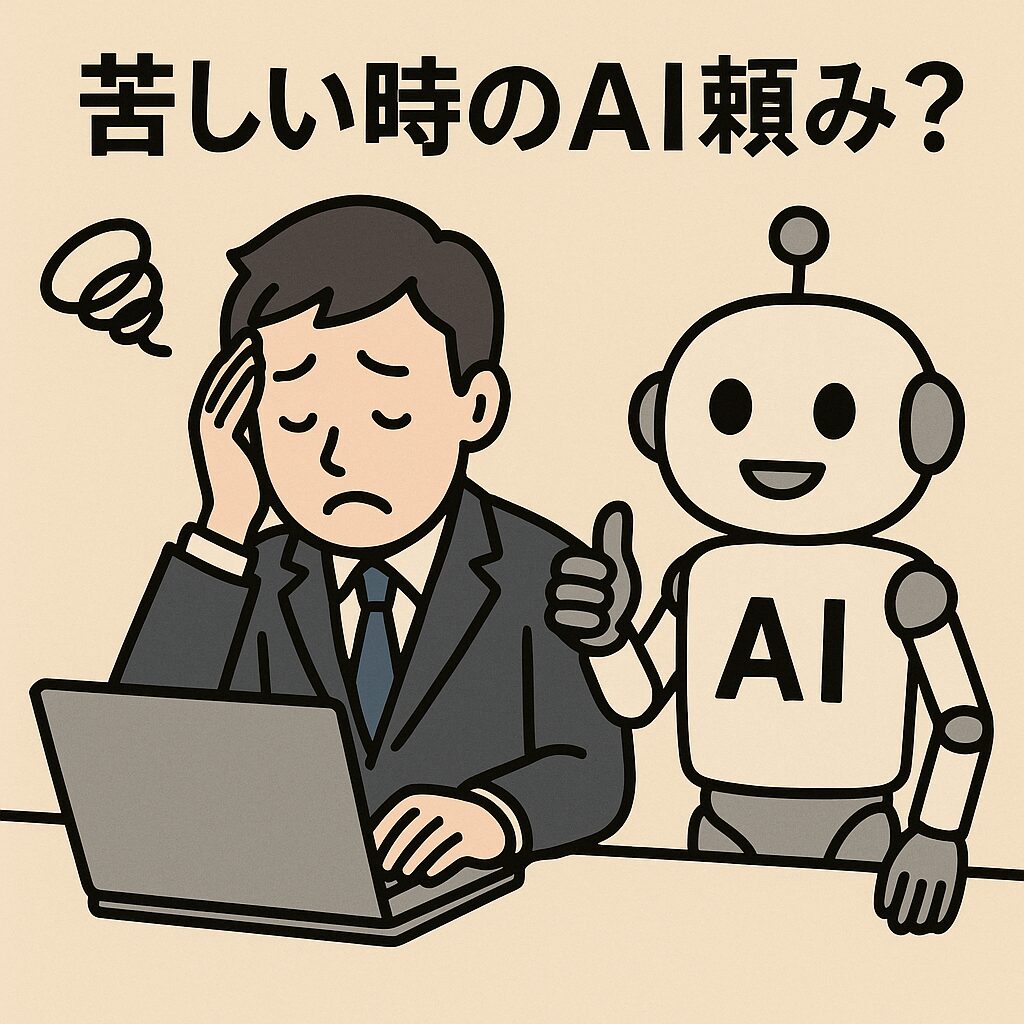
そこで今回はChatGPTに、現在の定跡事情について問いかけてみました。特に気になっていたのは「横歩取り」の現在です。
AI定跡とは何か?
ChatGPTの回答によると、以下のようなことがわかりました。AIが作った定跡(あるいはAIによって発見・再評価された定跡)はすでに存在します。
代表例として有名なのは「elmo囲い」です。2017年に登場した将棋ソフト「elmo」が示した囲いで、それまでプロでも使われていなかった形がAIによって有力とされ、現在ではトッププロにも定着しています。
また、AIは従来疑問視されていた形を再評価することにも長けており、これまでの常識を覆すような形が次々に生まれています。
横歩取りのAI流とは?
私はもともと振り飛車党なのですが、一時期この横歩取り定跡に凝っていた時期があり、当時は相横歩取りや内藤流3三角戦法が流行していたものです。あれから長い年月が流れ、結論が出たのかどうかがずっと気になっていました。
ChatGPTによると、現在の横歩取り定跡には以下のようなAI流の特徴があります:
- 角交換や囲いを急がず、タイミングを測る構想
- ▲7八金→▲5八玉→▲6八銀→▲7九玉と柔軟な囲い
- 後手は△5二玉や△3三角など軽い構えで柔軟に対応
かつて主流だった速攻の構えや馬作り重視の形は後退し、より「勝率に寄与する形」が選ばれる傾向になっています。つまりAIの定跡は、美しさよりも合理性と評価値重視なのです。
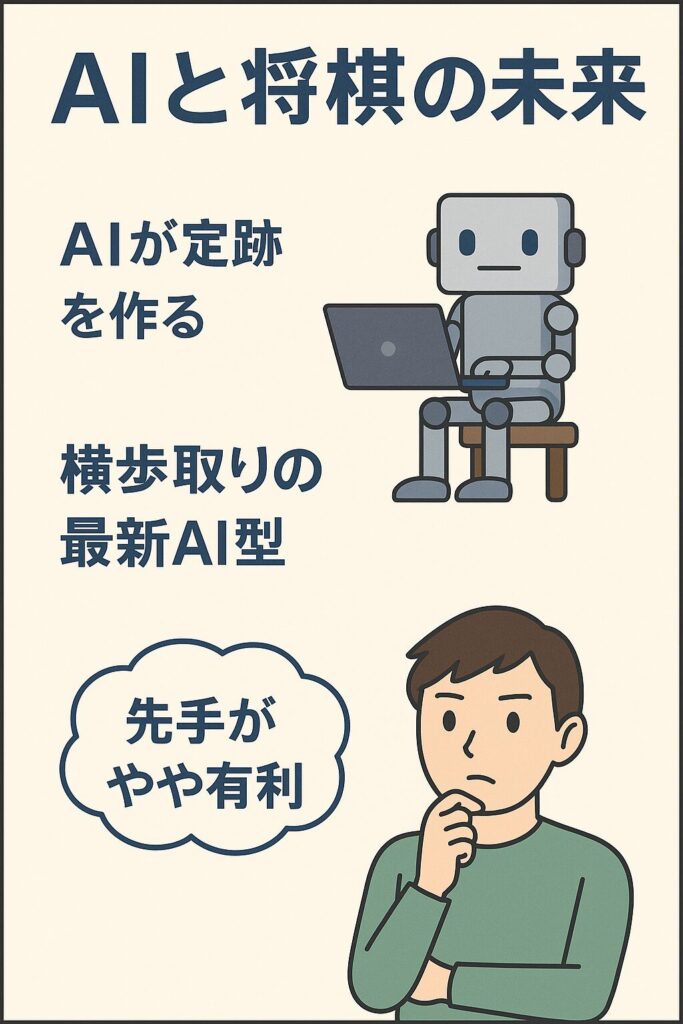
先手必勝法は現れるのか?
こうして見ていくと、やはり現在の主流は居飛車であることが改めて分かります。AIによって多くの戦型が分析されるなかで、振り飛車の勝率は居飛車よりも低いという評価が出ており、それが現代将棋の傾向に影響しているようです。
将棋AIは、すべての局面に評価値を与えることで、従来の曖昧な「形勢判断」から明確な勝率の世界へと移行させました。
将棋の未来を思うと、ふと考えてしまいます。
たとえば、矢倉や横歩取りといった戦型において、先手必勝法がAIによって本当に解明される日が来るのではないか……。2、3年前のデータでも、すでに先手勝率が後手をやや上回っていたことを思い出します。
果たして将棋は解明され尽くすのか、それともまだまだ無限の可能性を秘めているのか。
この問いに答えが出るのは、案外、そう遠くないのかもしれません。
将棋定跡の変遷とAIの衝撃 〜駒落ちの常識が変わる時〜の詳細はこちら