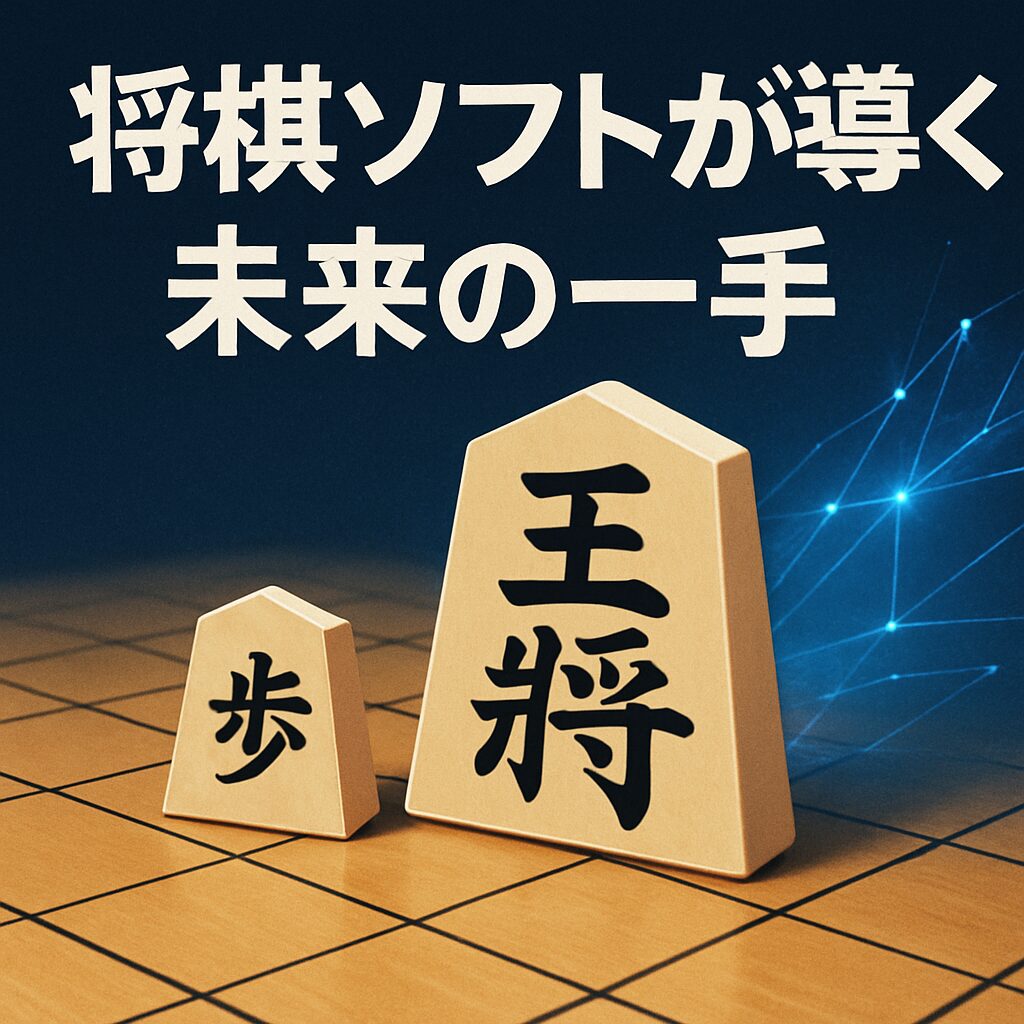昨日の投稿では、駒落ち将棋における「人間が考案した定跡」は、もはや過去の遺物と化しているという話をしました。従来の定跡が整合性の取れた、ある意味“聖典”のような存在だっただけに、私にとっては少なからず衝撃でした。
定跡に育てられた時代
私が若かりし頃――将棋に最も熱中していた1970〜80年代には、まだパソコンもネットも普及しておらず、定跡といえば本や雑誌が頼りでした。『近代将棋』などの月刊誌や、プロ棋士が書いた単行本をむさぼるように読んでいた日々。あの頃の私は、目にした一手一手を自分の中に蓄積し、定跡を“信じる”ことで上達を目指していました。
インターネットの登場で激変した将棋環境
ところが、時代は変わり、パソコンとインターネットの普及によって、将棋を指す環境も劇的に変化しました。24時間いつでも、誰とでも指せるネット将棋の登場は、まさに革命でした。結果として、本を読むことが煩わしくなり、テレビの将棋中継すらも遠ざかってしまいました。
最新定跡は“対局で学ぶ
こうして私は、30年近く将棋界の最新事情にすっかり疎くなっていました。若手プロの名前すら分からず、タイトル戦で初めてその存在を知ることもあるくらいです。流行戦法や新定跡も、もっぱらネット対局の中で「これはなんだ?」と直感的に感じることで初めて気づくのが常でした。
AIが導く新しい将棋
そんな中、私は再び興味を持ったのです。「AIが作った定跡」というものに。ChatGPTを通じて調べてみた結果、見えてきたのはAIならではの合理性と圧倒的な情報処理能力でした。驚いたことに、AIが提示する定跡はほとんどが居飛車。やはりAIは振り飛車を好まないのか、と考えさせられました。
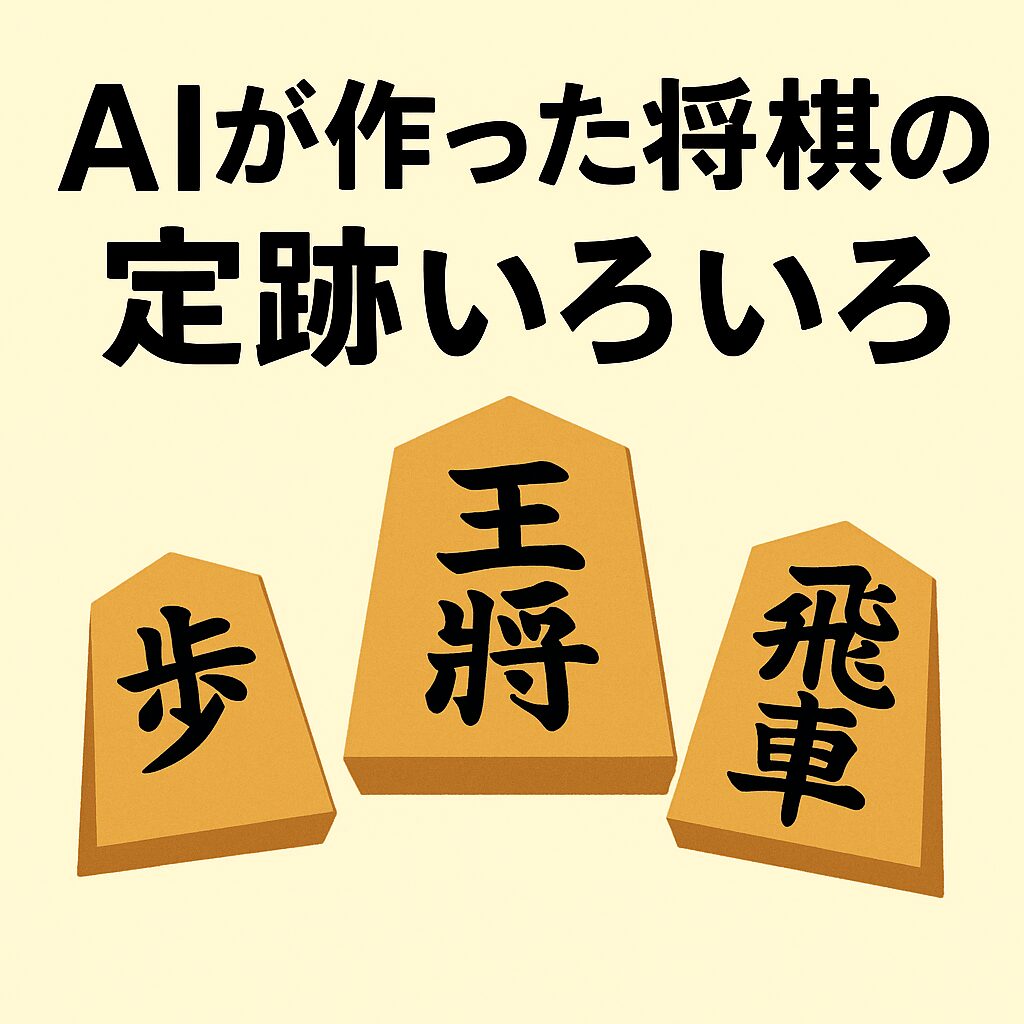
それらの定跡は、今では多くのプロ棋士も参考にしているといいます。藤井聡太さんも例外ではないでしょう。AIは知識・実力ともに“人智を超えている”存在なのだと、あらためて実感しました。
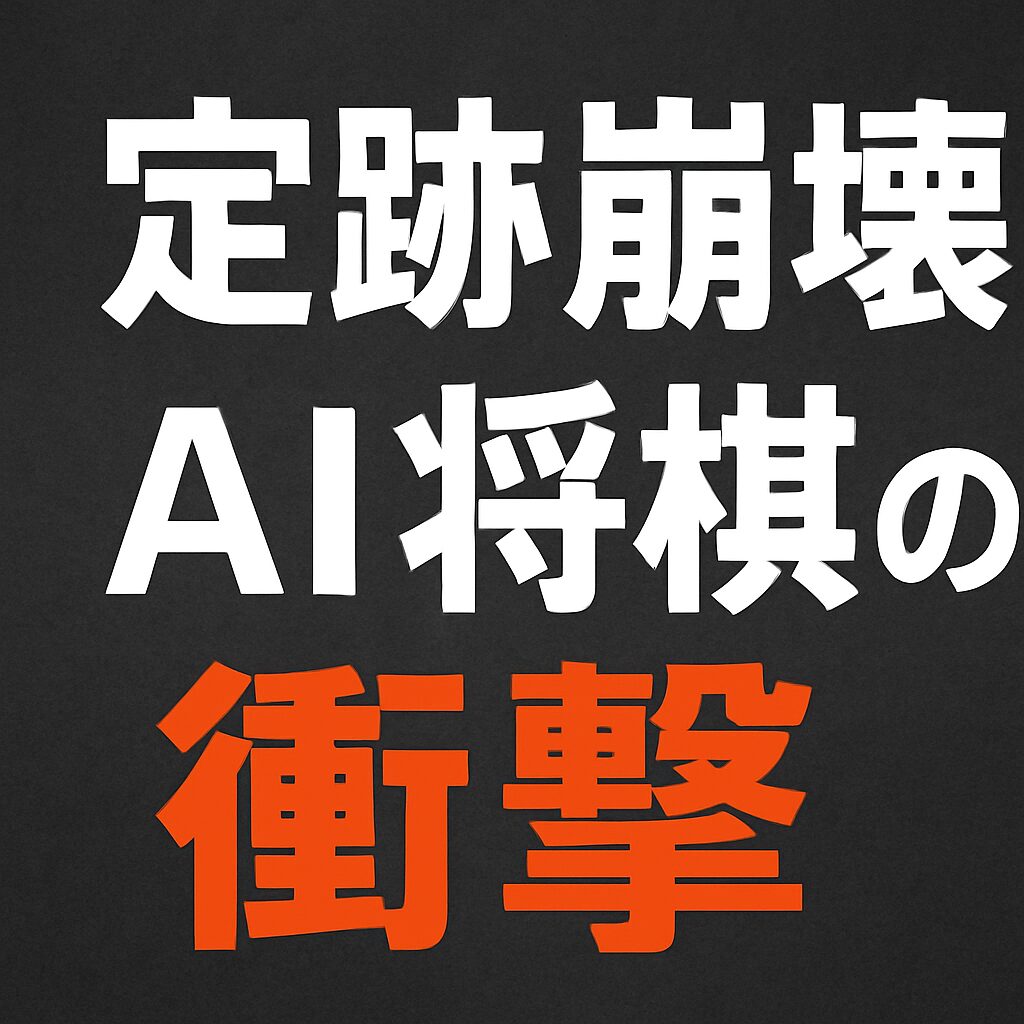
【結び】
駒落ち将棋に話を戻すと、ソフトが示す手は、人間が長年培ってきた定跡を“無視”しているようにさえ見えます。しかしそれは、無視ではなく「上書き」なのです。AIは、人間では到底たどり着けない一手を、正確に評価して選んでいるだけ。つまり“より優れている”から採用されているのです。
これからも私は、AIが示す新しい将棋の世界に目を開いていこうと思っています。次回は、そのAI定跡の中身について、もう少し掘り下げてみたいと思います。
次回予告タイトル案:
「AIが切り開く新たな定跡世界 ~振り飛車はなぜ消えたのか~」