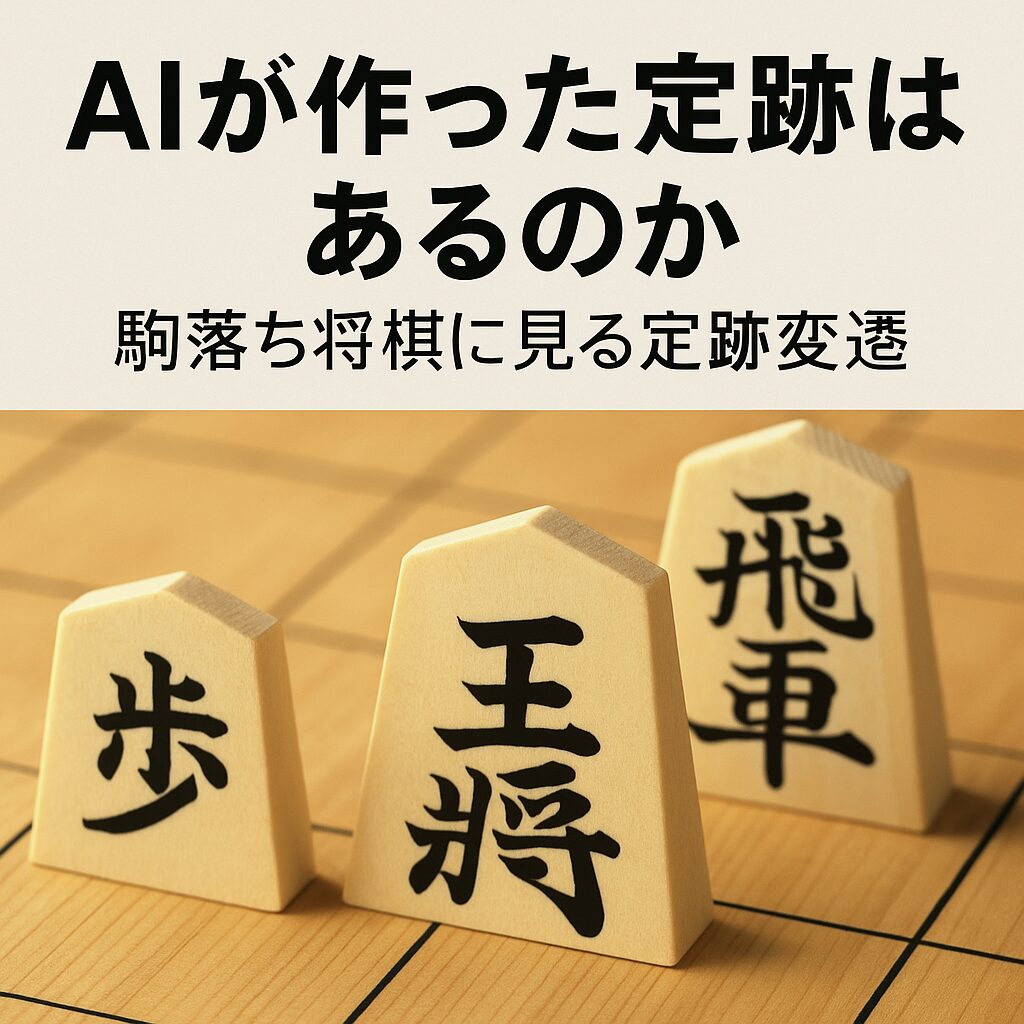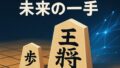AI時代の将棋に挑む
現在、私は将棋ソフトとの対局を主な楽しみにしています。かつてはネット将棋もよく指していたのですが、最近はご無沙汰です。自分が凝り性ということもあり、今では「駒落ち将棋」を中心に楽しんでいます。
使っているソフトは、以前にも紹介したことのある「水匠5」。非常に強力なAIで、現在は二枚落ちで対局しています。
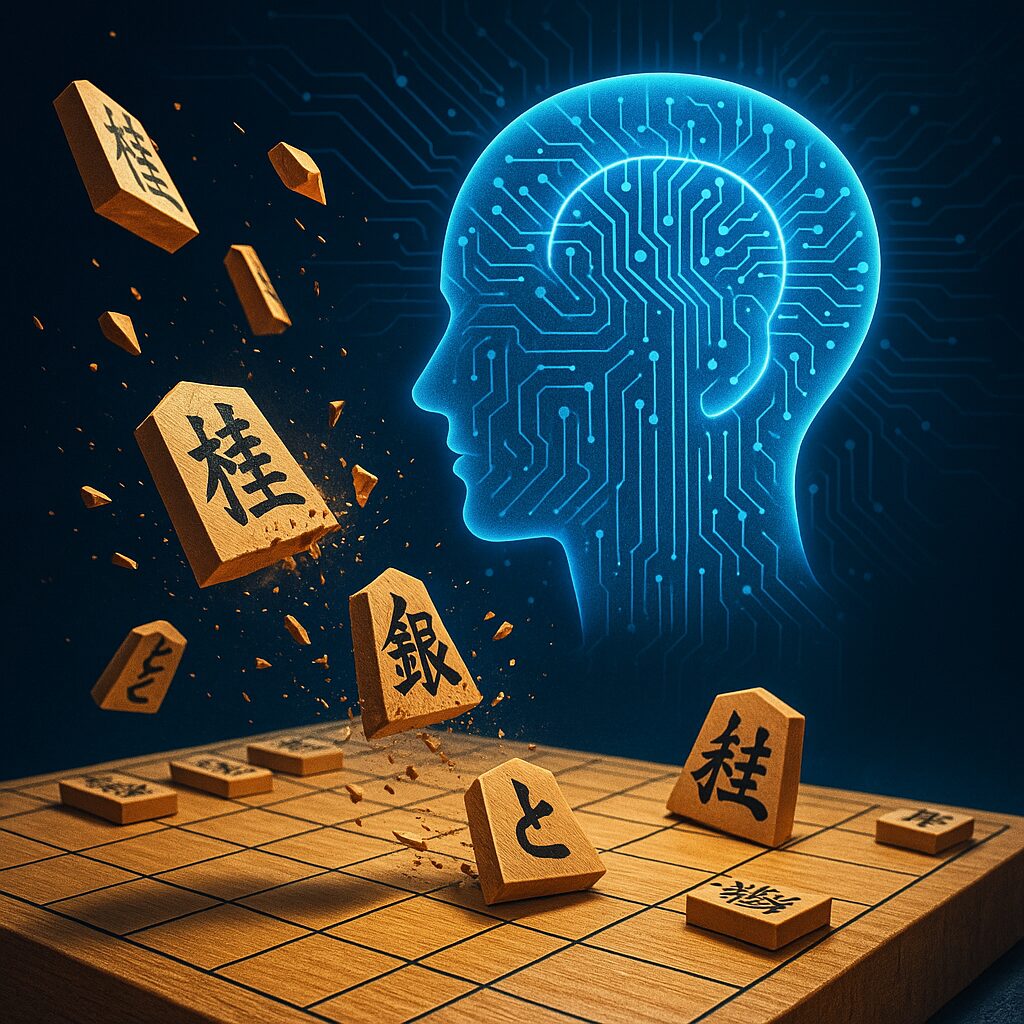
なぜ飛車落ちから二枚落ちへ?
1年ほど前までは飛車落ちで指していました。しかし、どうにも勝てないのです。相手の持ち時間は一手5秒と短いにもかかわらず、こちらの隙を見逃さず正確に指してきます。「待った」を何度も使っても、ほとんど勝てません。30局指しても勝てるのは1局程度。
「もしかして、手合い違いなのでは…?」
そう思い始め、試しに二枚落ちで対局してみたのです。
ところが、意外なことに結果は五分五分。四段の自分が、二枚落ちで五分とは…。このとき、AI将棋の強さをまざまざと感じたのです。
それをきっかけに方針転換を決意しました。
「まずは、二枚落ちで絶対に負けないようになる!」
これを目標に据え、現在も日々挑戦中です。
もうひとつの目標:直感力の養成
私はなるべく短時間で指すことも意識しています。
なぜなら、大会などで持ち時間が切迫したときに、悪手を指してしまうのを防ぎたいからです。直感で良手を選ぶ訓練を兼ねて、早指しにも取り組んでいます。
AIと定跡のズレ
さて、ここで本題の「定跡」について。
私自身、駒落ち将棋には実践経験が多く、将棋教室で指導していたこともあるため、それなりに自信があります。
ところが、将棋ソフトと飛車落ちで指していて驚いたことがあ四りました。
人間の定跡では、初手3四歩、以下7六歩と角道を開け、四歩で角道を止めるのが定跡でした。
ところがAIは――
**「角道?止めませんよ」**とばかりに、なんと3二金と指してくるのです。
角交換するならどうぞ、という構え。人間の定跡は、AIには通用しないのです。
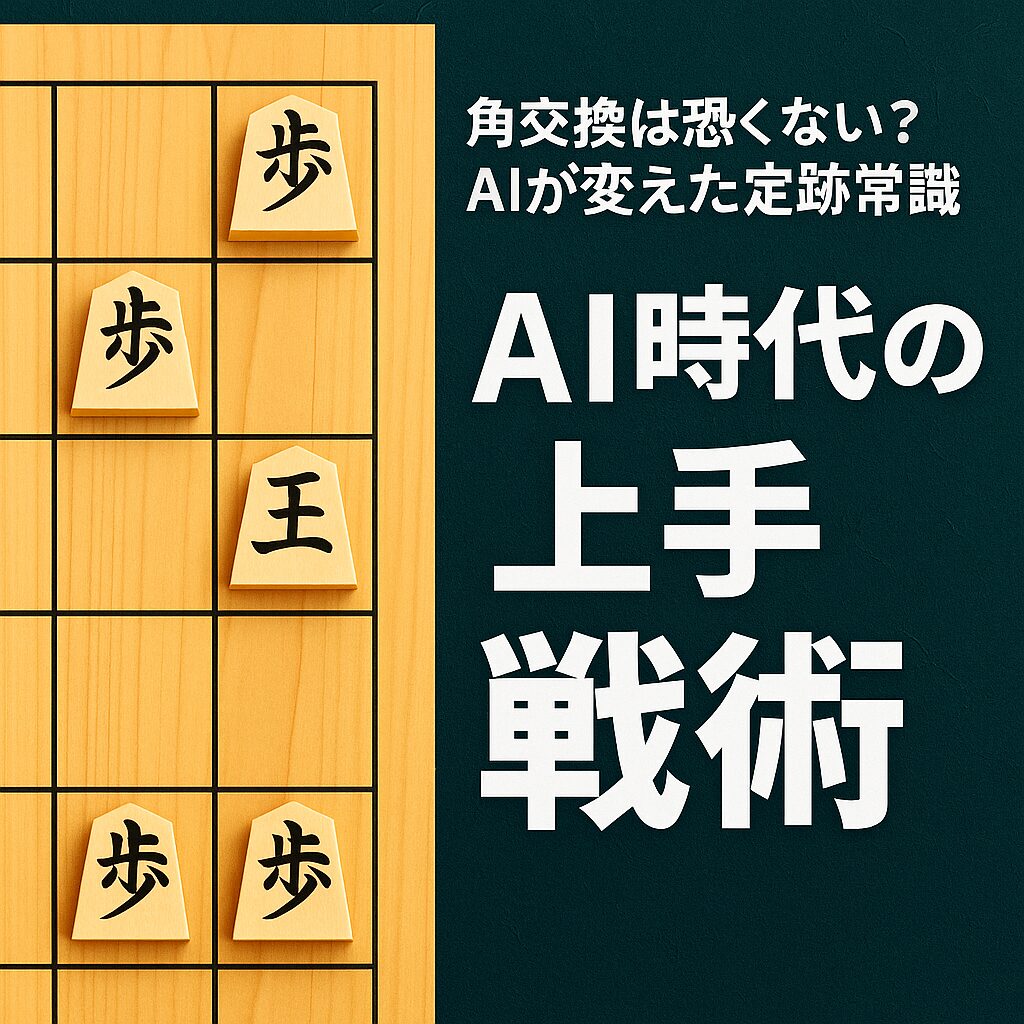
このように、将棋における「定跡」もAIによって再定義されつつある現代。
では、将棋ソフト自身は定跡をどう捉えているのか?
そして、AIが生み出した新たな定跡は存在するのか?
次回はその点に触れていきたいと思います。
それでは、また。