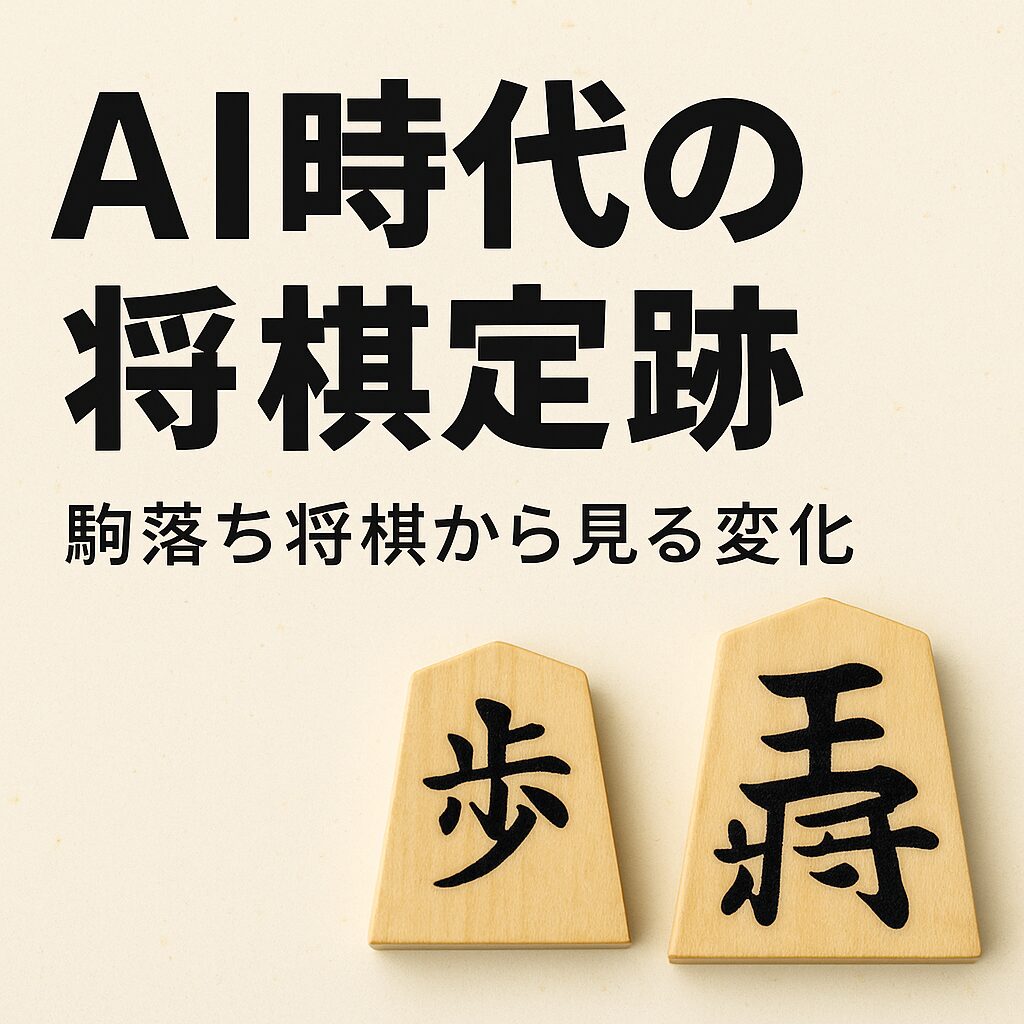~上達への最短ルートはここにある~
昨日までの投稿で、将棋レッスンにおいて駒落ち将棋を重点的に指導していたことについて触れました。今回は、なぜ私がそこにこだわったのか、その理由をお話ししたいと思います。
将棋レッスンの目的とは?
レッスンの目的はもちろん、将棋の楽しさを知ってもらうことです。しかし、やはり最も大切なのは「強くなること」。
そして「いかに早く上達できるか」が、指導する上での大きなポイントになります。
私自身の将棋上達体験
私が本格的に将棋にのめり込んだのは、上京したての19歳の頃でした。将棋の魔力に取り憑かれるように道場に通い、夢中で駒を動かし続けた日々――。
その後、四段になるまでにかかったのは、おそらく2〜3年ほどだったと記憶しています。
50年も前の話ですから、当然インターネットもなければ、将棋ソフトもありません。
**「将棋は人と指すもの」**という時代で、道場がすべての学びの場でした。
当時の道場では、有段者と級位者が指す際はハンデ戦、つまり駒落ち将棋が基本です。私も最初は二枚落ちから始め、角落ち、飛車落ちと進み、ついには平手で指せるようになりました。
なかでも忘れがたいのは、道場の席主との駒落ち対局です。あれが、まさに私が最も将棋が強くなったと感じた瞬間でした。
駒落ち将棋が上達の近道である理由
私の経験から言えるのは、上達の最短ルートは、上位者との駒落ち対局を数多くこなすことだということです。
その理由は、以下の2点に集約されます:
- 強い人と指さない限り、強くなれない。
自分より弱い相手との対局では得られるものが限られます。強い人と戦うことで、自分の弱点がはっきりと見え、克服する意識が自然と生まれます。 - 感想戦で得られる「気づき」が大きい。
対局後には必ず感想戦を行い、「ここが悪手です」「こう指せば良かった」など、上位者からの助言を直接受けられます。これが実に貴重で、自分の弱点と対策を明確に把握できるのです。
このような実体験を踏まえて、私は自分のレッスンでも**「駒落ち定跡」**をベースに指導することにしました。
駒落ち定跡は実力アップの宝庫
駒落ち定跡には、二枚落ち、角落ち、飛車落ちなどがあり、それぞれに定跡が存在します(※四枚落ち、六枚落ちなどもありますが、ここでは割愛します)。
昔はこれを徹底的に叩き込まれました。定跡通りに指すだけで、確実に下手(ハンデをもらう側)が有利になるのです。
駒落ち定跡書の最後には、こう記されています――
「これにて下手よし」
これは、「ここまでの指し方であれば、あとはどんな変化があっても下手が勝ちますよ」という意味です。
なぜ最後まで詰みまで解説しないかというと、途中の変化手順が膨大になるためです。紙面では収まりきらないため、「ここまでできれば十分」という締め方がされていたのです。
私は当時、これに大いに納得していました。
「先人が考え抜いただけあり、非の打ち所がない」――そう思っていたのです。
しかし、それを覆す出来事が…
ところが――。
この私の確信が木っ端微塵に打ち砕かれる出来事が後に起きます。
それは想像もしていなかった出来事であり、将棋観を揺るがす体験でもありました。
その話については、また別の機会に詳しくご紹介したいと思います。